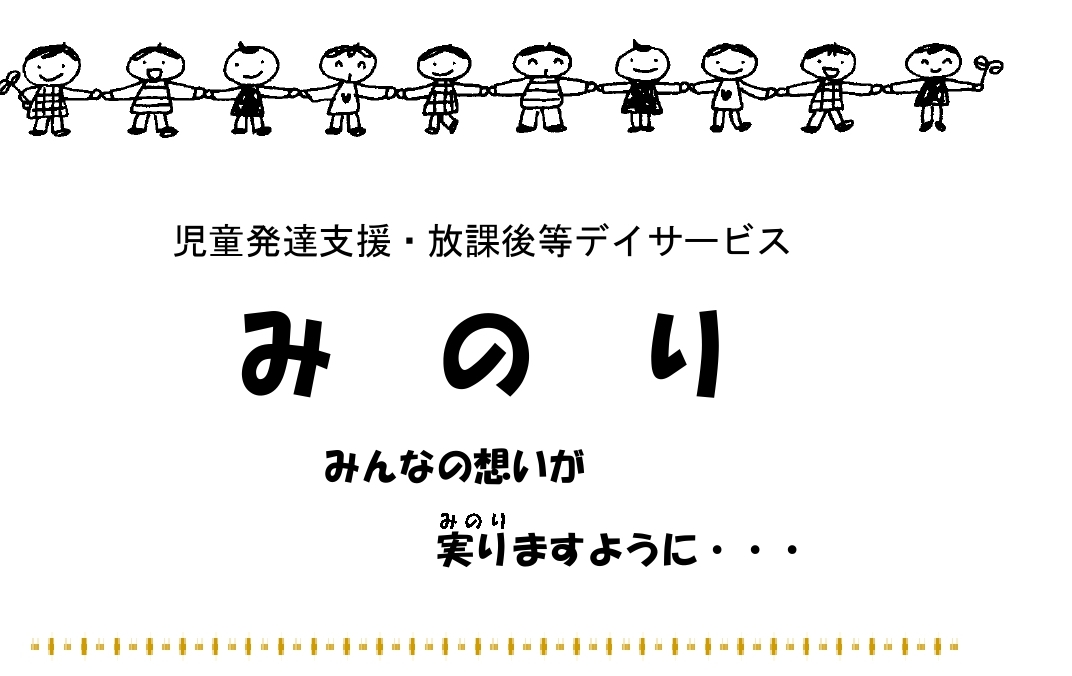5領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」つながる支援プログラムを作成しました。
健康・生活
・平熱を把握しながら表情などの視診も毎日行い家庭と連携を取りながら対応を考えます。また学校 などでいつもと違う活動や行事などがあると疲れが溜まり情緒が不安定になるので送迎時に必ず学校の様子を聞き、無理のないよう配慮します。
・身だしなみ、持ち物の管理、衣服の着脱など一人ひとりが無理なく自分できることを増やしていけるよう支援します。
・食べるということは食への欲求から自分の意思を出しやすくなります。また口の動かし方、手指の使い方、体の保持、意欲、満足感など様々な視点から子ども達の姿を把握し、支援できる大切な時間として捉え個別に支援を行っています。
運動・感覚
・ボール遊び・・・転がす、よける、投げる、受ける、つくなど一人ひとりの発達に応じた動きを誘導します。無理なく楽しいと感じながらできるようにしています。
・縄跳び・・・体幹、リズム感、協調運動など様々な要素が必要です。一人で飛んだり長縄跳びを使ってみんなで飛んだりしながら人への意識もできるよう支援しています。
・走る、追いかけなど人を意識しながら自分で体の使い方を調整したりできるようにします。
・五感を刺激する経験を重ね感覚の動きを豊かにできるようにします。
触覚・・・泡、片栗粉、小麦粉粘土、紙吹雪など
視覚・・・シャボン玉、プラネタリウムなど
聴覚・・・歌、音遊び
臭覚、味覚・・・クッキング
認知・行動
・一日の流れをボードや写真を使って自分で見通し持ち行動できるよう支援します。
・活動(遊び)の中で物の名前、大小、数、時間など身近などを理解できるよう支援します。
・散歩など自然に触れる機会を作り、身近な事象に興味を持てるようにします。
・様々な活動で楽しいと感じたり、もっとやりたいと意欲を持ったりして子どもの主体性を育てていけるようにします。
・共感したり認めたりしながら自己肯定感を高めていけるよう支援します。
言語、コミュニケーション
・安心できる人に自分の気持ちを伝えたいと強く思うことができるよう、気持ちを受け止め寄り添うことを大切にしています。その上で発語を促したり、語彙を増やしたり、写真、絵カード、表情、セスチャーなどコミュニケーションツールを広げていけるよう支援します。
・本人の意思を聞くときは一人ひとりの特性を理解した聞き方を取り入れ、本人の意思を尊重し、伝わった満足、安心感を重ねていくことも大切にし、意思表出ができるようにしています。
・集団生活の中で適切な言葉を使うことができるよう、その都度正しい言葉を伝えたりしながら人と関わる楽しさも感じていけるようにしています。
人間関係、社会性
・各機関と連携を取り多面的に子どもの姿を捉えながら子ども理解に努め、気持ちに寄り添っていけるようにしながら信頼関係を築いていきます。自分が大切にされているということを実感していくことが子どもたちの力を引き出し子どもたちが主体的に生活するための大きな基盤になっていくと考えています。
・地域の人と関わる機会を大切にし、社会のルールを知り、適切な行動が取れるよう支援します。
・活動(遊び)を通し、自分から大人、友達へと人に対する関心を高め、模倣したり自分で工夫したり考えたり、また友達と一緒に協働作業したりしながら人との関わり方、自分の感情のコントロール仕方などを身に付けていけるように支援します。